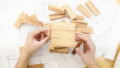今、世界のニュースの多くは、米国とイスラエルを巡る中東情勢、そしてロシアとウクライナの戦いに注目が集まっています
確かにこれらは非常に重要な問題ですが、その「舞台の裏側」で、したたかに、そして着実に存在感を増している国があることをご存じでしょうか? それが「インド」です
先日ブラジルで開かれたBRICS首脳会議で、インドのモディ首相が際立った存在感を示したというニュースがありました
中国の習近平国家主席も、ロシアのプーチン大統領も対面での出席を見送る中、モディ首相は議長国ブラジルの大統領と並んで写真に収まり、積極的に各国首脳と会談したそうです
金融機関で、世界の政治経済の大きな流れが、市場やビジネスにどう影響するかを見てきた私からすると、このインドの動きは、単なる外交ニュースではなく、今後の世界秩序、そして私たちのビジネス環境にも大きな影響を与える可能性を秘めていると感じています
今回は、なぜ米国・中ロの対立の陰でインドがこれほど存在感を増しているのか、その背景と狙いを考えてみます
なぜ今、インドが世界の注目を集めるのか?〜その背景とモディ首相のしたたかな狙い〜
世界が主要な紛争や対立に注目する中で、なぜインドはこれほどまで存在感を増しているのでしょうか?
そして、BRICS首脳会議でモディ首相が見せた外交姿勢の裏には、どんな狙いがあるのでしょうか?
(1)世界第1位の人口大国と高い経済成長率
まず、インドは世界最大の人口(約14億人)を抱え、近年目覚ましい経済成長を続けている国です
若い労働力が豊富で、巨大な消費市場としても期待されています
→経済的なパワーが、国際社会での発言力を高める大きな土台になっています
(2) 米欧と中ロ、どちらにも偏らない「バランス外交」の追求
今回のニュース記事で最も重要なポイントの一つが、インドの「バランス外交」です
米欧との連携も強化
インドは、米国、日本、オーストラリアとの協力枠組み「Quad(クアッド)」にも参加し、外相が米国で友好的な関係を強調しています
また、モディ首相は先日カナダで開かれたG7(主要7カ国)首脳会議にも招待されており、米欧との経済・安全保障面での連携も重視しています
中ロの枠組みにも参加しつつ距離を置く
一方で、ロシアや中国が主導する上海協力機構(SCO)にも加わっています
しかし、モディ氏は2024年のSCO首脳会議には参加せず、国防相会合での共同声明への署名も拒否するなど、中ロに無条件で同調するわけではない、という姿勢を明確にしています
(3) 「グローバルサウスの盟主」としての自負
モディ首相がBRICS開幕スピーチで「グローバルサウス(新興・途上国)の利益は優先されていない」と述べたように、インドは新興・途上国のリーダー(盟主)としての役割を強く自任しています
「多国間主義」の推進
インドは、一国が巨大な力を持つ「一極主義」ではなく、多くの国が協力して世界的な問題を解決する「多国間主義」を掲げています
BRICSは、そのための重要な「プラットフォーム(基盤)」の一つだと位置づけているのです
開発志向のBRICSへの回帰
「中ロが米欧への対抗軸としてBRICSを利用する色が濃くなった」という現状に対し、インドは「敵対ではなく共存」へと軌道修正を狙っています
今回の会議では、「開発協力」「スタートアップ・エコシステム」「再生可能エネルギー」といった、新興国の発展に直結する、より実用的な議題を掲げ、先進国の知見や資金力も必要とする分野での協力を促しています
つまり、インドは、米欧と中ロの対立を傍観するだけでなく、その間で独自の道を歩み、新興・途上国の代表として、世界のルールメイキング(ルール作り)に積極的に関与しようとしているのです
今後のBRICSとインドの動き〜「IBSA」の再注目と中国との主導権争い〜
今回のBRICS首脳会議では、特に以下の点が今後のインドの動きを占う上で注目されます
(1) 「中ロ不在」の活用とBRICSの軌道修正
習近平国家主席とプーチン大統領が対面出席を見送ったことは、インドにとってBRICSの主導権を握る「好機」となりました
「反米欧」からの脱却
インドは、BRICSが「反米欧」の枠組みになることを望んでいません
中ロが不在の間に、BRICSを「共存」の方向へと軌道修正し、西側諸国とも協力できるような、より柔軟な組織へと変えていこうとするでしょう
活発な外交アピール
モディ首相が全参加国首脳と会談する意向を示し、相手国の言葉でXに発信するなど、活発な外交姿勢をアピールしたのも、インドの存在感を高める狙いです
(2) 「IBSA」の再注目
BRICSの中で、インド、ブラジル、南アフリカの3カ国(IBSA)という枠組みが再び注目されています
共通の価値観
これらの国々は、多民族国家であることや、民主主義という共通の価値観を持っています
開発志向
「IBSAは本質的に開発志向のグループだ」と専門家が指摘するように、中ロのような「米欧への対抗」ではなく、「開発と協力」に重点を置く姿勢が共通しています
BRICS内の多様性維持
IBSAがBRICS内で存在感を増すことで、BRICSが中国とロシアの影響下に過度に置かれることを避け、より多様な意見を持つグループとしてのバランスを保とうとする狙いもあるでしょう
(3) 中国との「グローバルサウス」主導権争い
インドは「グローバルサウスの盟主」を自任していますが、同じく新興国を代表しようとする中国との間には、水面下で「主導権争い」があります
インドの台頭が、社会人を目指す私たちに与える影響
インドのしたたかな外交戦略と国際的な存在感の向上は、決して他人事ではありません。
(1) ビジネスチャンスの拡大
巨大市場の成長
インドの経済成長は今後も続く見込みであり、巨大な消費市場としての魅力は増す一方です。日本企業もインドへの投資や事業展開を加速させるでしょう
多様な協業の可能性
IT、製造業、エネルギーなど、様々な分野でインド企業との協業の機会が増える可能性があります。金融SEとして、インドのIT人材や開発手法に触れる機会も増えるかもしれません
新たなサプライチェーン
中国一辺倒だったサプライチェーンを分散させる動きの中で、インドは重要な代替生産拠点となりつつあります
(2) 国際情勢の複雑化とリスク管理の重要性
「多極化」する世界
米欧と中ロという二つの極だけでなく、インドのような第三極が台頭することで、世界はより「多極化」していきます。これは、国際関係がより複雑になり、予測が難しくなることを意味します
金融市場の変動
各国のバランス外交や、特定のブロックに偏らない動きは、金融市場にも新たな変動要因をもたらす可能性があります
投資やビジネスにおいて、より多角的な視点からリスクを評価し、分散する能力が求められるようになります
日本の外交・経済戦略の再考
インドの動きは、日本の外交や経済戦略にも影響を与えます
私たちも、インドとの関係強化や、グローバルサウスとの連携をより重視していく必要があるかもしれません
【まとめ】インドの「したたかさ」に学ぶ未来
米国とイスラエル、ロシアとウクライナという大きな対立の陰で、インドは独自のバランス外交を駆使し、「グローバルサウスの盟主」として国際社会での存在感を急速に高めています
BRICS首脳会議での主導権発揮は、その象徴と言えるでしょう
このインドの「したたかな外交」は、今後の世界を読み解く上で非常に重要な視点を与えてくれるのではないでしょうか