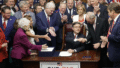突然ですが、「1.4京円」って、どれくらいの金額か想像できますか?
「京」というのは、1兆の1万倍、日本国の予算(一般会計)が約110兆円なので、その100倍より大きい数字なのです
このとてつもない金額が、今、世界の金融市場に、ある「隠れた借金(隠れ債務)」として存在し、国際決済銀行(BIS)という、世界の金融を監視するとても大切な機関が「これは危ない!」と強く警鐘を鳴らしています
しかも、この隠れた借金のほとんどは「米ドル」なんです。
今回は、このBISが警鐘を鳴らす「米ドルの隠れ債務」とは一体何なのか、なぜそれが危ないのか、そしてもし何か起きた時に、私たちの社会や生活にどんな影響があるのかを、一緒に考えていきましょう
「為替スワップ」という見えない借金〜
「為替スワップ」は、ちょっと難しい言葉ですが、将来の約束事の取引だと思ってください
もっと簡単に言うと、こんなイメージです。
【為替スワップのイメージ】
例えば、日本の銀行が今すぐ米ドルが必要だとします
でも、単に円をドルに両替するだけでなく、こんな取引をするんです
今、円を貸して、ドルを借りる(交換する)
〇〇ヶ月後(例えば3ヶ月後)に、借りたドルを返す代わりに、今貸した円を返してもらう
この時、借りたドルには利息をつけて返す、という約束をする
これだけ聞くと、普通の短期的なドル借り入れのように見えますよね
でも、これがなぜ「隠れ債務」と呼ばれるかというと、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)という銀行の公式な「家計簿」に、この「ドルを返す義務」がはっきりと借金として載らないことが多いからなんです
まるで、家計簿に書かれていない「内緒の借金」みたいなものです
しかも、この取引の多くは満期が1年未満の短期商品で、どんどん期限が来ては新しいスワップでドルを借り直す、という形で続けられています
なぜ「隠れ債務」が急増しているの?〜増え続けるドルの需要〜
BISがこの「隠れ債務」に警鐘を鳴らす最大の理由は、その規模がものすごく大きくなっていることです
2008年末(リーマン・ショック直後): 約41兆ドル(約6京円)
2023年末: 約91兆ドル(約13京円)
2024年末時点: 約98兆ドル(約14京円)
たった15年ほどで、なんと2倍以上に膨れ上がっているんです!
なぜ、こんなに増えているのでしょうか?
それは、世界中で米ドルの需要が増え続けているからです
グローバル経済の「共通通貨」: 貿易や投資など、国際的な取引の多くは米ドルで行われます。世界中の企業や銀行が、事業を行うために米ドルを必要としています
米国外の銀行の需要: 特に、アメリカ国外に本社を置く銀行が、米ドルを必要としているケースが多いと推計されています
そして、さらに見過ごせないのが、この「為替スワップの最大の利用者は、ノンバンク(銀行ではない金融機関、例えば投資ファンドや保険会社など)である」というBISの指摘です
ノンバンクは規制が緩い
銀行は、国や国際機関から厳しいルール(規制)が課せられ、どれくらいの借金をしていいか、どれくらいのドルを確保しておくべきか、といったことが厳しくチェックされています
でも、投資ファンドや保険会社といったノンバンクは、銀行ほど厳しい規制が及びにくいんです
情報開示も不十分
彼らがどれくらいのドルを、どんな方法で調達しているのか、具体的な情報が外からは見えにくいのも問題です
つまり、「どこに、どれくらいのドル建ての隠れた借金があるのか、そしてそれがどれくらい危険なのか、全体像が把握できていない」という、非常に危険な状況だということです
もし「ショック」が起きたら何が起こる?〜流動性危機と日本のメガバンク〜
では、もし世界経済を揺るがすような「ショック」(例えば、大きな金融危機や戦争、パンデミックなど)が起きたら、この「隠れ債務」がどんな問題を引き起こすのでしょうか?
潜在的なリスクが膨れ上がっていることを意味し、何か起きたときの影響はそのぶん大きくなると言われています
(1) 「ドル不足」が広がる「流動性危機」
想像してみてください
もし、たくさんの企業や銀行が「今すぐドルが必要だ!」となったらどうなるでしょうか?
ドルの奪い合い
みんなが一斉にドルを求めると、市場でドルが不足し、ドルを借りるコスト(金利)が急激に上がります
まるで、品薄の人気商品の値段が跳ね上がるのと同じです
資産の投げ売り
ドルを確保できない金融機関は、ドルを返すために、持っているドル建ての資産(アメリカの株や債券など)を売却せざるを得なくなります
これが一斉に起きると、資産の値段が暴落し、金融市場全体が混乱に陥ります
財務の悪化
ドルを高いコストで借りたり、資産を安値で売却したりすれば、金融機関の経営状況は一気に悪化し、最悪の場合、倒産するような事態に発展しかねません
これが「流動性危機(りゅうどうせいきき)」と呼ばれるものです。
ちょうど新型コロナウイルスが広がり始めた2020年には、世界中で金融機関や企業が一斉にドル確保に動き、実際に市場でドル不足が広がりました
その時は、アメリカの中央銀行(FRB)が、日本の中央銀行(日銀)などを通じて大量にドルを供給することで、なんとか危機を乗り越えました
(2) 日本のメガバンクも他人事じゃない?
実は、日本の大手銀行、特に三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの3メガバンクも、このドルの調達に課題を抱えていることが指摘されています。
これらの銀行は、海外の企業などに対し、たくさんの「外貨貸出金」(ドル建ての融資)を行っています
でも、それを賄うだけの「外貨預金」(ドル建ての預金)が十分にありません
「預貸率」が100%超え
3メガバンクの「預貸率」(外貨預金で外貨貸出金をどれだけ賄えているかを示す比率)は、いずれも100%を超えています (三菱UFJFGが109%、三井住友FGが131%、みずほFGが127%)
つまり、預金だけでは貸出金を賄えていない状態です
不足分はスワップなどで調達
不足しているドルは、社債を発行したり、為替スワップのような金融派生商品を使ったりして調達しているんです
その額は、三菱UFJFGが約820億ドル、三井住友FGが約1460億ドル、みずほFGが約937億ドルに上ります
これはつまり、もしドル不足のショックが起きた時に、日本のメガバンクもドルを調達するのが難しくなるリスクを抱えているということです
「有事のドル供給」は今後も続くのか?〜トランプ政権と中東情勢の影〜
前回のコロナ危機では、FRBが大量のドルを供給して事態を収拾しました
しかし、今後もFRBが同じようにドルを供給してくれるのか、市場には疑問の声があります
(1) 「第2次トランプ政権」の動き
BNPパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミストは、「グローバル金融危機が発生した際、FRBが主要国の中銀にドルを供給するのか極めて不確実になってきた」と指摘しています。
なぜなら、第2次トランプ政権は、基軸通貨であるドルを世界に供給するコストを巡り、各国にも相応の負担を求めようとしているからです
「なぜアメリカだけが、世界の金融危機にドルを供給するコストを負担しなければならないのか?」という考えが、政策に反映されていけば、有事の際のドル供給がスムーズに行かれないかもしれません
(2) 中東情勢という不安要素
さらに、緊張が続く中東情勢も不安要素です
可能性は低いものの、もしホルムズ海峡の封鎖などで原油価格の異常な高騰が長期化すれば、世界的に景気が悪化し、金融機関がお金を貸し渋る「信用収縮」を招く可能性があります
そうなると、資金の出し手がいなくなり、さらにドルの「流動性」が逼迫することになるでしょう
【まとめ】「隠れ債務」は私たちの生活と無関係じゃない!
国際決済銀行(BIS)が警鐘を鳴らす米ドルの「隠れ債務」は、目に見えにくいからこそ、その危険性が過小評価されがちです
しかし、その規模はすでに1.4京円に達し、もし金融ショックが起これば、世界の金融市場、そして私たちの生活にも大きな影響を与える可能性があります
見えない借金が膨張:
為替スワップを使ったドル調達は、貸借対照表に載りにくく、その実態が掴みにくい
ノンバンクでの増加
銀行に比べて規制が緩い投資ファンドなどで利用が広がっていることが、リスクをさらに高めている
日本のメガバンクも課題
日本の大手銀行も、ドル調達に為替スワップなどを利用しており、ドル不足のリスクを抱えている
「有事のドル供給」の不確実性
次の危機でFRBが以前のようにドルを供給してくれるか、トランプ政権の政策によっては不透明さが増している。
この「隠れ債務」の問題は、私たち個人の生活に直接「1.4京円」がのしかかるわけではありません
しかし、もし金融危機が起きれば、経済が不安定になり、株価が下がったり、金利が上がったり、企業が倒産したり、失業者が増えたりする可能性があり、それは、私たちの給料や貯蓄、さらには将来の安定にも大きく影響してくるのです