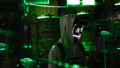あなたは、自分のSNSアカウント、仮想通貨、オンラインゲームのデータ、どうなるか考えたことがありますか?
今までは、土地や家といった不動産、株券や現金通帳といった「モノ」があったのですが、Bitcoinのような仮想通貨はどうでしょう。金融機関のサイトにアクセスしようにも、パスワードがわからずひらけないとか・・
従来の相続とは違うデジタル資産特有の難しさや今すぐやるべきことをお伝えいたします
デジタル資産って何?その種類と相続の難しさ
デジタル資産は多岐にわたりますが、利用者からみて、大きく3つに分けてられます
・財産的価値を持つもの
・思い出や記録の価値を持つもの
・利用権・アクセス権の価値を持つもの
例えばでいいますと、「財産的価値をもつデジタル資産」としては、
暗号資産(仮想通貨: ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)など)
NFT (Non-Fungible Token):
デジタルアート、ゲーム内アイテム、トレーディングカードなど)
オンライン証券・FX口座の資産
電子マネー・オンライン決済サービスの残高(:PayPay、Suica、Amazonギフト券など)
オンラインゲーム内の資産・アイテム
また 「思い出や記録の価値を持つデジタル資産」としては
クラウドストレージ内のデータ(iCloud、OneDrive に保存された写真、動画、文書など)
SNSアカウントのデータ(Facebook、LINE、ブログなどの投稿、メッセージ履歴、写真など)
メールアカウントのデータ
デジタル写真・動画
また、「利用権・アクセス権の価値を持つもの」としては
サブスクリプションサービスのアカウント(Netflix、Amazon Primeなどの有料会員情報)
オンラインバンキング・証券口座のアクセス権
ECサイトのアカウント
いかがでしょう
思った以上に、たくさんあると思われませんか
ご自身でも分からなくなるときがあるのに、相続される家族が把握するのは至難の業かと思います
大切な家族に対してであっても、お話しませんよね
またPaypay残高は相続できますが、ポイントは相続できないとか、相続できるものと出来ないものがあるので、注意が必要です
金融機関はデジタル資産の相続に”及び腰”?
従来の金融システムはデジタル資産の管理には対応しきれていません
なぜならば、既存の勘定系システムがデジタル資産に対応しきれていないからです
既存の勘定系システムは、銀行口座の残高は、メインコンピュータで一元管理をしているのですが、
複雑な仮想通貨やNFTは、ブロックチェーンのような「分散型」の仕組みをベースに作らているので
銀行の「中央集権型」システムの根本的な違っているのです
セキュリティとリスク管理の壁
デジタル資産の相続はセキュリティ面で非常に高いリスクを伴います。
相続時の厳格な本人確認、不正アクセスからの保護、万が一の情報漏洩時の責任問題など、銀行が負うリスクの大きさはとても大きくて、コストや要員面からもとても難しいからです
法整備と運用でも課題
国内法規が未整備であったり、デジタル資産を管理しているのが海外だったりすると、金融機関がデジタル資産を「保管」したり「移転」したりする上での法的な責任とコストが大きくなって対応が難しいのです
相続人からの問い合わせに対する対応フローもまだまだ未確立な状態です
デジタル資産相続の具体的なリスクと対策
個人でもできるデジタル資産を相続する「デジタル終活」で今からできる対策があります
最も重要なのは「パスワード管理」です
パスワードリスト(手書きでも可)を作って、信頼できる人への預けることですが、
パスワード管理ツールの活用(LastPass, 1Passwordなど)を活用することはおすすめです
また「死亡時にアクセス権を付与する」機能を持つサービスも出てきていますので、それを活用
することも検討してよいかもしれません
デジタル遺言・エンディングノートの活用
「どのデジタル資産を、誰に、どうしてほしいか」を具体的に書き残すことが大事です
ご自身がもっている資産はご自身でしかわからないですよね
ログイン情報、URL、サービス名、意向などをリスト化するとよいと思います。
重要な情報なので、保管方法に注意が必要です
専門家への相談
弁護士や信託銀行、デジタル遺品整理サービスなどの活用することも有用です
生前からの家族とのコミュニケーション
デジタル資産の存在を家族に伝え、いざという時の対応を話し合っておくことの重要性です
【まとめ】デジタル化が進む未来と、新たな役割
未来の金融機関は、従来の資産だけでなく、デジタル資産の管理や相続にも対応できるよう、
システムの進化と法整備への提言が求められますので、徐々に整備されてくると思います
一方で、自分の資産は自分で守ることが重要ですので、今日からできる「デジタル終活」を
始めてみるのはいかがでしょう